子ども理解に裏打ちされた、厚みのある実践を続けてこられた長岡文雄氏。
本書は1975年の古い書籍ですが、今読んでも古さをまったく感じさせず、教師としてのあり方を考えさせられる名著です。
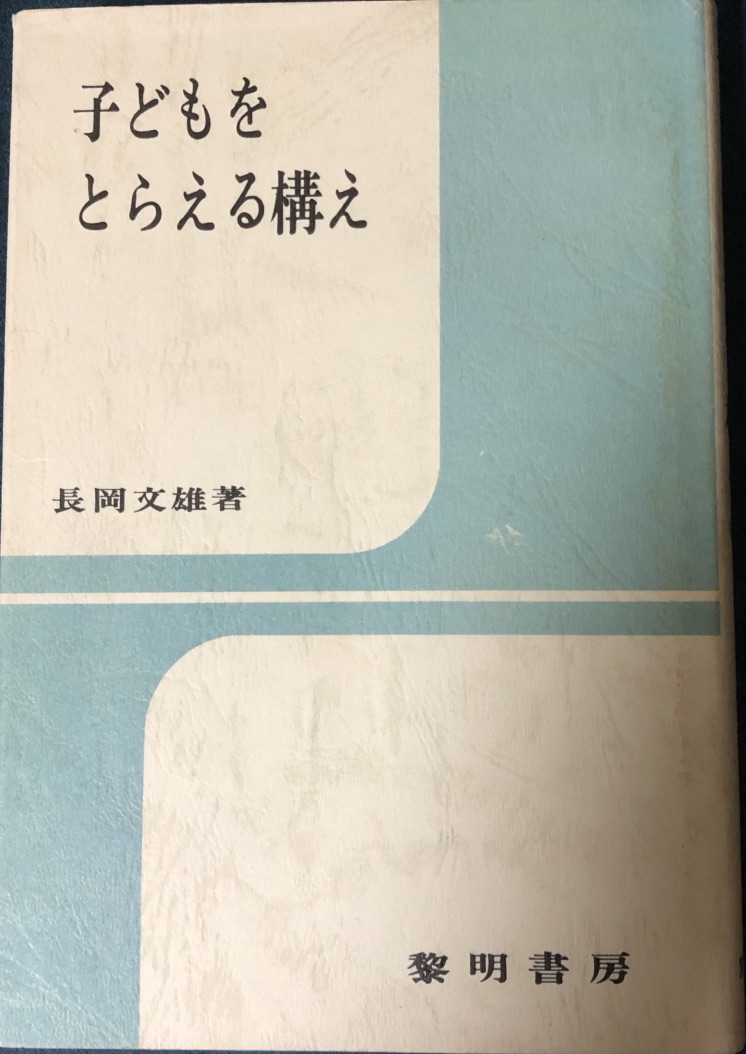
以下、本文の中にある長岡氏の言葉を紹介いたします。
〇一般に、「授業は子どもを教える場だ」と考えられている。しかし、わたくしは、あえて、「授業は子どもをさぐる場だ」と自分に言い聞かせている。
〇「真に教える」ということは、「子どもをさぐることのなかにしか成立しない」ということが、身にしみてわかってくるのである。
P10子どもや父兄に「先生」と呼ばれるうちに、いつの間にか、教師になりたてのころに味わった「子どもに対するこわさ、わからなさ」「人間に対処する敬虔さ」を忘れていく。
あつかましくなるにつれて、「子どものことはわかっている」と思い、「自分の教えることは、必ず子どものためになる」と考えやすくなる。
教師が、子どもに対して、「よかれかし」と、善意をこめてやっていることがらでも、半分ぐらいは、子どもの成長の邪魔をしているように思われてくる。
〇教育は、何といっても、ひとりひとりの子どものためにしかない。教育は、ひとりひとりの子どもが、人間としての可能性をぎりぎりまで発現していくようにてつだうことであり、個性的思考の深化を支援して人間としての生き方を創造させることである。
〇子どもは、教師がいるいないにかかわりなく刻々と動く。子どもは、教師が「教えた」と思っていることだけで成長するわけではない。したがって、教師は、広い視野で、しかも長い目で子どもを追いつづけなければならない。そうでなければ、真の子どもの思考体制に迫ることはむずかしい。
教師は、教師である限り、どんなにいそがしくても、子どもひとりひとりを熟知しないではおられない。子どもをさぐらないで教師となることはできないからである。
とくに重要なことは、教師がこのようにして、子どもに迫ることが、とりもなおさず教師の人間としての自己変革の過程であるという自覚である。「教師になる」ことは、子どもに驚くことであり、子どもに学ぶことであろう。
〇「子どもを知らずには、子どもの育てようがない」という姿勢に徹したとき、教師の眼は、教育の眼となるのである。
そして、とくに自覚したいことは、子どもをとらえるという営みが、そのまま、「教師が人間として子どもに学ぶことだ」ということである。
子どもに迫って、近づくほど、教師も自らを一皮むかねばならないはめに陥る。
〇教師は、子どものつくる授業を構想し、「考えあう授業」を臨んでいる。それは、子どもたち自身で大洋に船を乗り出させるようなものである。嵐に遇ったとき、それだけの復舷力もつかで真の実力は問われる。
〇子どもをさぐろうとすれば、どうしても教師自身が、子どもに学んで自己変革を遂げなければならなくなるものである。
〇わたくしは、かつて次のような恥ずかしい思いをしたことがある。それは卒業式のときのことである。当時二年生の担任であったので、「子どもがさわがねばよいが」と念じた。それで、朝、式場に出かける直前に、わたくしは、重ね重ね、「静粛に行儀よく」という注意をした。そうすると、式が予想以上にりっぱにできたのである。わたくしは「やっぱり注意をしたのがよかったんだ」と、内心喜んだ。
ところがどうであろう。卒業式の作文には、「きょうは、ひとりずつ台の上に上がる六年生の靴がめずらしいので、わたしはそればっかり見ていました。すると式はすぐに終わりました」というのがあらわれたのである。わたくしは、ひとりよがりのおめでたい評価をしていた自分に気づき、穴にもはいりたい気持ちになった。
〇教育の根底は人間理解であり、教師と親や子どもとの信頼関係である。教師のやりがいのある楽しい指導は、みんなが自分を裸にして、明るく積極的に行きあうことによって成立する。子どもは「先生が自分のことをよくわかってくれている」と思えば、自然に大胆な行動をとる。そして、少々行きすぎても、いざというときには、教師のもとをはなれない。教師とともに船に乗り組み、嵐に立ち向かう。さか巻く波にもまれても復舷する。そこに人間として生きる子どもと教師の共感がある。